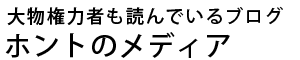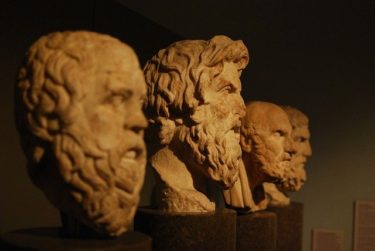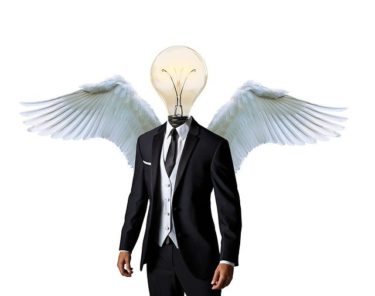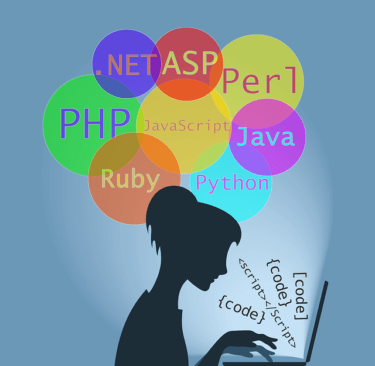どうも、武信です。(No998)
僕は2019年に目標を立て、結局達成できないまま終わったので2020年は目標を一切立てないで過ごしました。
その結果「ホントのメディアの約996記事到達!&リライトも720記事以上」を達成しました。(「文章力も向上した」と思います)
また、会員制ブログに仕様を変更しました。
ツイッターフォロワー数もだいたい150前後から880ぐらいまで増えました。(地道に相互フォロー作戦や風林火山などの企画に参加しました)
ブログデザインも大幅に進化しました。(これが一番成果がでかいかもしれません)
りゅうけんさんのオンラインサロンに入ったり(1ヶ月で辞めましたが)、NoCodeWalkerのオンラインサロンに入ったり、いろいろと動きました。
安倍も倒れ、僕に追い風が吹いてきたように感じます。
2020年の漢字を表すと「耐」ですし、今まで生きてきてずっと「耐」が僕を一番表す漢字だったと思います。
2021年から何か動きがあるでしょうかねー。
今回、珍しく「2021年のだいたいの目安・方向性を考えておこう」と思い、記事化します。
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 僕のビジネスの方向性。
まず、僕のビジネスの方向性として以下が考えられます。
1 Flierのようなサブスク課金サイト。
2 NoCodeに特化したコンテンツサイトやNoCode案件をやるかNoCode開発指導。
3 ライティング系オンラインサロン。
4 ライティングの仕事をやる。
5 これらの複合型。
1に関しては僕1人でFlierのような何十人もいる相手とまともに戦って勝てるとは到底思えません。
要約コンテンツですが、おそらく社員がけっこういて(外部委託含む)、コンテンツ生産量が膨大になっており、僕1人で作れるコンテンツ量とはかけ離れています。
しかも、WebデザインもサービスもFlierのほうが上です。
僕は「要約サービスというコンテンツ」では勝負するつもりはありませんが、ビジネス書系やDaiGoと似ている、「人の役に立つ系」コンテンツという枠組みでは一緒だと思います。
要約ではなく、僕の解釈や知見や考察を取り入れたり、書評系のコンテンツにする予定です。
しかし、問題なのが仮に僕が頑張って200記事の有料記事を書き上げたとしても「有料会員は1ヶ月で全ての200記事を読んで退会してしまうのでは?」という恐れです。
もちろん月に10記事は新規更新するつもりですが、10記事程度だと継続課金しないと思うのです。
月額480円くらいだったらビジネス書本(約1800円)☓10冊=18000円分のコンテンツが480円で読めるので割に合うかも知れませんが。(僕の解釈・知見・考察も加わるのは強みです)
また、ビジネスが軌道に乗れば、仲間を集いさえすればFlierに対抗できるかもしれません。
月にビジネス書20冊の新規登録が加わると1800円☓20冊=36000円分になり、かなりお得になります。
そして、毎月480円が継続的に入ってきますし、20冊☓12ヶ月、つまり1年続けると有料コンテンツが240になります。
最初は僕だけの頑張りで200記事ぐらい用意しておき、それプラス240の有料コンテンツが加わり、440コンテンツになります。
2年目は440コンテンツ+240=680コンテンツになります。
680もあると膨大な量になり、数カ月は課金して居続けてくれるかもしれません。
年数を重ねれば重ねるほど有利になるビジネスがサブスクモデルです。(資産型ビジネスです)
これに、オンラインサロンやライティング指導なども加えたら、お得感がさらに増すかもしれません。
2の「NoCodeに特化したコンテンツサイトやNoCode案件をやるかNoCode開発指導」に関してはNoCodeを作るのはやはりこれからのトレンドになりそうだからです。
まぁ、1の知識系コンテンツのサブスクに進むかNoCodeに進むか、で明暗が分かれそうです。
過去のビジネス書蓄積の観点から言えば1を選んだ方が僕の強みは活かせます。
また、NoCodeで何かアプリを作り、それを普及させて僕のホントのメディアを広告で載せたら、宣伝になります。
アプリを作り、流行らせたいのはそういう目的もあったのです。
3の「ライティング系オンラインサロン」に関してはやるべきかなと思います。
1のサブスクに付け加えたら強いです。
ライティングに限らず、オンラインサロンサービスを付け加えると継続課金してくれるかもしれません。
何しろ月額480円ですからね。
4の「ライティングの仕事をやる」は「誰かからライティングの仕事を請け負い、書く」か、または「ライティングの指導をする」という意味です。
5の「複合型」はまさに今まで言ってきた通り、組み合わせるということを指します。
ちなみに月額480円と設定しましたが、変動する可能性はあります。
2 ふろむださんのビジネスモデル。
番外編としてふろむださんのビジネスモデルは「あり」かなと思いましたが、本人から「儲かりませんよ!」とツイッターに返信がありましたし、僕も納得し「ほそぼそと稼ぐにはいいかもしれないなぁ」と感じました。
ふろむださんのビジネスモデルは以下だと思われます。
1 有料本(「学習効率本」など。約2000円で高額)を持っている。
2 ライティングオンラインサロン経営。(サブアカウントで文章力クラブを主催しています)
3 ツイッターや市販の紙の本で知名度を得て、宣伝し、誘導している。
コスパが悪く、労力の割には儲からないと思われます。
しかし、LTV(生涯顧客価値)で考えた場合2000円以上の利益を読者が購入してくれた数で得ているわけですね。
学習効率本は1980円であり、第5巻までありますが1巻目はお試しで無料です。
ふろむださんの電子書籍店は以下です。
仮に1980円☓4冊で4冊全巻買ってくれて、7920円だとすると1人の顧客が7920円払ってくれるわけです。
僕のようなオンラインサロン(月額480円)なら7920円に達するには16ヶ月ぐらいかかります。
僕の方が分が悪い気がします。
しかも、ふろむださんは今後も有料電子書籍を追加していけばいいだけです。
僕の場合は1人で1ヶ月に最低でも10記事は更新します。
そして、僕の場合継続課金し続けてくれる保証はありません。
ですが、オンラインサロンを付け加えたり、ライティング指導などをつけるとお得感がでて、継続課金してくれるかもしれません。
ふろむださんのビジネスモデルはサブスクではなく、売り切り型モデルです。
ですが、コンテンツビジネスとして新しいやり方かもしれません。
個人電子書籍店ですからね。
しかも、ライティングのオンラインサロンも並行してやっています。
また、ふろむださんの場合ライティングスクールの弟子?の出版物をふろむださんの電子書籍店で売ることもできそうです。
「個人電子書籍店+オンラインサロン」というビジネスモデルは「あり」かもしれないと感じます。
3 僕が考えたビジネスモデル。
で、僕は以下のビジネスモデルを考えました。
ホントのメディアを母艦にし、広告塔の役割とします。
NoCodeに手を仮につけてWebアプリを作り、流行ればホントのメディアを宣伝します。(これはやるか不明です)
ホントのメディアの有料課金型サブスクサイトを作ります。(まず200記事は用意します)
その後定期的に月に10記事以上は書き、コンテンツを貯め込んでいきます。
サブスクモデルは年月が経てば経つほど有利になり、誰も追いつけなくなる資産型モデルなのです。
さらに、ふろむださんのように有料のビジネス大著を書くには僕にはハードルが高いので、もっとライトな著書を書き、電子書籍店で発表します。(1冊、500円程度です)
加えて、オンラインライティングサロンを運営し、弟子?を指導し、弟子?の本も電子書籍店で売り出します。
また、サブスクの有料ホントのメディアは月額480円くらいにし、オンラインライティングサロンも付け加えて、お得感を出します。
ライティングの情報交換の場を作りますが、個別のライティング指導に関してはきちんと金をとります。
それにしても、ふろむださんの学習効率本の「いいね数」を見てみると、1冊につき最大で約100ぐらいであり、そんなに売れていないようなんですよね。
「Flierもどれくらい儲けているか?」不明です。
やはり、コンテンツビジネスの主役は動画に移ったのでしょうか?
DaiGoが大儲けしていることからも読み取れます。
まだまだ先が見えません。
4 僕が特に今年やることと、やらないこと。
僕が今年やることとやらないことを、仕事面を中心にして、書きますね。
やることの筆頭格と言ったら読書です。
今まで、無駄な情報(ツイッターやYahoo記事など)を入手しすぎました。
ツイッターやYahoo記事よりもやはり本のほうが質が高いので「本をもっと読みたい」と思います。
コンテンツ作りとして、本に労力を以前より割き、コンテンツ強化していきたいのです。
僕にあまり関係ないニュースや記事は極力スルーしていきたい所存です。
つまり、以前よりやらないことは「ツイッター情報収集&Yahooなどの記事を読むこと」であり、以前よりやることは「本を読むこと」です。
YouTube動画は今までのように作業中に聞き流しします。
ではこの辺で。(4146文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。